学資保険は年末調整で生命保険料控除が利用できる
なぜ学資保険は年末調整で税金が戻ってくるの?

学資保険の税金
学資保険を掛けているサラリーマン家庭の場合、年末調整で税金が戻ってきます。
学資保険はお子さんの学費を貯める手段として知られているものですが、れっきとした生命保険だからです。
積立貯金と異なり学資保険では、被保険者が死亡または高度障害となった場合に、その後の保険料支払いが免除されるうえ、保険金を受け取ることができます。
そのため、学資保険は年末調整で生命保険料控除の対象となり、所得から一定金額の保険料が控除されるのです。
課税対象となる所得が多いほど税金の金額は高くなりますが、所得控除を受けられると課税対象額が少なくなるため、その分税金が安くなるのです。
サラリーマンの場合、あらかじめ給与から毎月の源泉徴収によって税金が差し引かれています。
そして年末に再計算して過払い分が払い戻される仕組みになっています。
これが学資保険で税金が戻ってくる理由で、医療費控除や住宅ローン控除なども、生命保険料控除と同じように税金が戻ってくるものとしてよく知られています。
生命保険の控除には3種類ある
生命保険料控除とは、1年間に支払った一定の保険料が契約者のその年の所得から控除されることで、所得税と住民税が軽減されるというものです。
生命保険料控除には3つの区分があり、それぞれについて同等の控除を受けることができます。
3つの区分は以下の通りです。
| 1. 一般生命保険料控除 | 民間生命保険会社の生命保険契約や、農業協同組合や全労済などの生命共済が対象 |
| 2. 介護医療保険料控除 | 医療費や介護料金に対して保険金が支払われる契約や、疫病や身体の障害などに対して保険金が支払われる簡易保険契約が対象 |
| 3. 個人年金保険料控除 | 厚生年金や国民年金以外に個人が任意で加入している年金保険契約が対象 |
学資保険は死亡保険・養老保険・収入保障保険などと同じように、1の一般生命保険料控除に区分されています。
がん保険や医療保険は2の介護医療保険料控除に区分されているものです。
なお、いずれに分類されるかは特約などの名称ではなく、保障内容によって決定されます。
詳細は加入している保険の生命保険会社などに問い合わせて確認されることをおすすめします。
また、傷害特約や災害割増特約などの保険料については、平成24年以降は生命保険料控除の対象から外されています。
そのため、実際に支払っている保険料と生命保険料控除証明書に記載されている保険料の金額が異なるケースもあるため、注意が必要です。
年末調整で戻ってくるのは所得税と住民税
年末調整で税金が戻ってくることはよく知られていますが、この税金は所得税と住民税の2種類が合算されたものです。
所得税の場合、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除それぞれの適用限度額は、最大で40,000万円となり、住民税の場合だとそれぞれ28,000円となります。
なお、3つの控除を合計した適用限度額は所得税120,000円・住民税70,000円(28,000円×3ですが、84,000円にはなりません)で、それぞれの内訳と金額は以下の通りです。
| 所得税 | 住民税 | |||
| 区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
| 一般生命保険料 ・ 介護医療保険料 ・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) | 20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | (払込保険料×1/2) +10,000円 | 12,000円超 32,000円以下 | (払込保険料×1/2) +6,000円 | |
| 40,000円超 80,000円以下 | (払込保険料×1/4) +20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 | (払込保険料×1/4) +14,000円 | |
| 80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 | |
平成23年末までに加入した保険の場合は?
生命保険料控除は、平成22年度の税制改正によって制度が変わりました。
そのため、平成23年12月31日以前に契約した保険は、旧制度の生命保険料控除が適用されます。
旧制度では介護医療保険料控除の区分はなく、一般生命保険料と個人年金保険料の2種類の区分でした。
旧制度の所得税での最大適用額は、一般生命保険料・個人年金保険料のそれぞれ5万円ずつで、住民税の最大適用額はそれぞれ3万5千円となっています。
それぞれの内訳と金額は以下の通りです。
| 所得税 | 住民税 | |||
| 区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
| 一般生命保険料 ・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) | 25,000円以下 | 払込保険料全額 | 15,000円以下 | 払込保険料全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | (払込保険料×1/2) +12,500円 | 15,000円超 40,000円以下 | (払込保険料×1/2) +7,500円 | |
| 50,000円超 100,000円以下 | (払込保険料×1/4) +25,000円 | 40,000円超 70,000円以下 | (払込保険料×1/4) +17,500円 | |
| 100,000円超 | 一律50,000円 | 70,000円超 | 一律35,000円 | |
配偶者名義でも申告OK
学資保険の生命保険料控除は、年末調整をする人の名義でないものも申告できます。
例えば契約者が妻で、保険料を支払っているのが夫という学資保険の場合です。

配偶者名義でも申告OK
生命保険料控除の対象となる契約は、保険金の受取人が契約者本人または配偶者、その他の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)であるものです。
つまり、問われているのは保険金の受取人が誰であるかで、契約者は誰であっても構いません。
実際に保険料を支払っている人が控除を受けることができるため、契約者が妻であっても夫の年末調整で控除を受けられるのです。
ここで注意したいのは、「年末調整で戻ってくるのは所得税と住民税」の項で解説したように、生命保険料控除には上限があるということです。
学資保険を含む生命保険の保険料が、上限の年間8万円を超えていた場合、超えた部分は無駄になってしまいます。
一般に、夫の生命保険だけで8万円は超えてしまうことは多いため、学資保険の生命保険料控除証明書が余ってしまっているのではないでしょうか。
もし妻が所得税を支払っているなら、余っている夫名義の生命保険料控除証明書を妻の年末調整で活用すれば無駄になりません。
この場合、保険料を誰が支払っているのかを明確にしておく必要があります。
控除を受ける人の金融口座から保険料が引き落とされるようにしておくと、保険料を支払っている事実を客観的に証明できます。
なお、保険料を払う人と契約者は同一であるほうが自然です。
契約者の名義は実際に保険料を支払っている人にしておくことをおすすめします。
契約者の変更手続きはほとんどの場合、書類に必要事項を記入して添付書類をそろえて郵送すれば完了します。
手続き用の書類は、保険会社に連絡すれば送付してもらえます。
学資保険の控除はいくら?
学資保険の控除は最高4万円
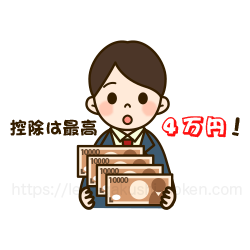
学資保険の控除は最高4万円
「年末調整で戻ってくるのは所得税と住民税」の項でご紹介したように、平成24年1月1日以降に加入した保険の場合では、一般生命料控除の適用限度額は所得税で40,000円となっています。
学資保険はこの一般生命料控除に区分されるため、最高で40,000万円が所得から控除されることになりますが、夫や妻の生命保険などのような一般生命保険料控除に区分される保険に加入している場合は、それらを合算して考えます。
もし学資保険を年間80,000円支払っていれば、他の生命保険料をいくら払っていたとしても、控除額は上限額の40,000円となるのです。
多くの家庭では学資保険の保険料として毎月10,000円程度支払っているため、上限の80,000円は軽く超えてしまうようです。
ただし、所得税に加えて住民税においても生命保険料控除が適用されます。
住民税では年間保険料が56,000円を超えた場合、控除額は最高で28,000円となり、所得税と合わせると68,000円が所得から控除されます。
なお実際に戻ってくる税金と控除額とは異なり、こんなに多くはありません。
所得税の場合は年収によって税率が変わってきますが、年間課税所得が195万を超え330万円以下の場合で10%となります。
課税対象額は年収とは別物で、所得税率が10%になる年収の目安は500万から600万円です。
住民税は年収にかかわらず一律10%となっています。
所得税率が10%の方が年間に一般生命保険料として合計80,000円を支払っている場合なら、実際に戻ってくる税金は所得税が4,000円、住民税が2,800円で合わせて6,800円となるのです。
別枠で税金が戻ってくることも
先に解説したとおり、学資保険の保険料は一般生命保険料控除の区分に該当します。
学資保険に医療保障の特約を付加している場合には、介護医療保険料控除の対象にも該当する場合があるのです。
この場合、一般生命保険料控除に加えて介護医療保険料控除の枠からも税金が戻ってきます。
一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除として、所得税と住民税の課税対象所からそれぞれ40,000円と28,000円ずつが控除されるため、一般生命保険料控除の上限に達していても、介護医療保険料控除に区分される学資保険があれば、別枠で税金が戻ってくるのです。
現在加入中の学資保険がどの区分に該当するかについては、毎年10月から11月ごろに生命保険会社から送付されてくる「生命保険料控除証明書」に記載されているので、よく確認していただければと思います。
この「生命保険料控除証明書」は、生命保険料控除を受けるために必要なものなので、年末調整まで大切に保管しておいてください。
実際私もよくあるのですが、この生命保険料控除証明書が送られてくるのが秋ごろで、年末調整までに時間があり、つい、どこにしまったかを忘れてしまうことが多々あります。
また、郵便で送られてくるため、自分がポストから出さなかった場合、家族が取り入れたそのまま気づかず、どこかに紛れてしまうことさえあります。
保険をかけている人は秋ごろに「生命保険料控除証明書」が送られてくるということを気にかけ、しまっておく場所も忘れないようしっかり決めておいたほうがいいかもしれませんね。

なお、万一「生命保険料控除証明書」を紛失してしまった場合は、再発行してもらえます。
再発行の手続きは、インターネットや電話から行うことができ、手続き完了後おおむね1週間程度で、新しい「生命保険料控除証明書」が郵送されてきます。
再発行を急いで行いたい場合には、生命保険会社の店舗窓口で手続きすれば、最短だとその場で再発行してもらえます。
生命保険料控除の申告方法
申告しなければ税金は戻ってこない

学資保険の生命保険料控除申告
ここまで、学資保険で生命保険料控除を受けた場合、いくら税金が戻ってくるかについて詳しくみてまいりましたが、ここで最も重要なことをお伝えしなければなりません。
それは、『生命保険料控除を受けるためには、毎年申告しなければならない』ということです。
いくら保険料をたくさん支払っていても、申告しなければ税金は1円も戻ってきません。
さらに、保険内容に変更がなくても毎年申告しなければならないのです。
サラリーマンの場合、自動的に毎月の給与から源泉徴収で税金を徴収されているのに、払いすぎた税金を取り戻すために毎年書類をそろえて申告しなければならないことに納得のいかない方は多いでしょう。
しかし、申告しなければ税金は戻ってこないというシステムを変えることは、残念ながらできません。
きっちりと毎年申告して払いすぎた税金を取り戻していただくために、ここからは学資保険で生命保険料控除を受けるための申告方法を、詳しく解説していきます。
サラリーマンは年末調整で申告
会社に勤めているサラリーマン(給与所得者)の方が学資保険の控除申請を行うのは、年末調整のときです。
多くの場合、会社から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入したうえで、保険会社から送付された年間の払込保険料が記載されている「生命保険料控除証明書」を添付して勤め先に提出すれば、会社が手続きを行ってくれます。
具体的な記入方法は以下のとおりです。
・「保険会社等の名称」の欄:学資保険に加入している保険会社の名称を記入しますが、略称でも大丈夫です。
| 「保険等の種類」の欄 | 「生命保険料控除証明書」に記載されている「種類」を記入します。 |
| 「保険期間又は年金支払期間」の欄 | 「生命保険料控除証明書」に記載されている「期間」を記入します。 |
| 「保険等の契約者の氏名」の欄 | 「生命保険料控除証明書」に記載されている契約者の氏名を記入します。 |
| 「保険金等の受取人の氏名」の欄 | 「生命保険料控除証明書」に記載されている受取人の名前を記入します。 |
| 「あなたとの続柄」の欄 | 控除申請している本人の場合は「本人」、違う場合は「配偶者(夫または妻)・父(祖父)・母(祖母)・子」のいずれかを記入します。 |
| 「新・旧の区分」の欄 | 「生命保険料控除証明書」に記載されている「区分」を記入します。 |
| 「あなたが本年中に支払った保険料等(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)の欄 | 「生命保険料控除証明書」に記載されている「金額」を記入しますが、共済などで支払い保険料の剰余金が返還されている場合には、控除後の金額を記載してください。 |
| 「給与の支払者の確認印」の欄 | 勤め先が使う欄なので、何も記入しないでください。 |
金額欄は、同じ区分・種類の金額を合計して記入しますが、計算の方法は「給与所得者の保険料控除申告書」の左下に記載されているので、それを参考にすれば大丈夫です。
新旧や一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の区分を間違えないように注意しましょう。
なお、年度の途中で退職してその年度内に再就職していない方の場合、年末調整は行われません。
そのため学資保険などの控除を受けるためには、自分自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告の方法は、次の「自営業者は確定申告で」の項で詳しく解説します。
自営業者は確定申告で
サラリーマンであれば会社が年末調整をしてくれますが、自営業者や個人事業主の場合、そうはいきません。
また、先の章でふれた年度内に再就職しなかった中途退職者の場合も同様です。
このような方々が学資保険の保険料控除を受けるためには、自分自身で確定申告を行う必要があります。
自営業者の方は、翌年の2月16日~3月15日まで(原則、土・日曜にあたる場合は受け付けていません)に行う確定申告の際に、申告書の生命保険料控除欄へ必要事項を記入して、「生命保険控除証明書」とともに税務署へ提出します。
中途退職者の方は、「確定申告書A第一表・第二表」の生命保険料控除欄に必要事項を記入したうえで、「生命保険控除証明書」と「源泉徴収票」を添付し、税務署に提出または郵送します。
住民税の控除は別途行う必要はなく、所得税の手続きだけで大丈夫です。
確定申告書の入手は、以下のいずれの方法でも可能です。
- 税務署に取りに行く
- 申告相談会場で受け取る
- 税務署に電話して送付してもらう
- 国税庁のホームページからダウンロードして印刷する。
確定申告を行う場所は、原則として1月1日に住民票がある自治体内の税務署となっています。
控除額の計算は、「生命保険の控除には3種類ある」の項に掲載した、区分ごとの所得税と住民税の控除額を示した表を参考に行ってください。
確定申告書の書き方は、まず確定申告書A第二表の「生命保険料控除」欄に年間保険料を転記します。
続いて、確定申告書A第一表の「所得から差し引かれる金額」にある「生命保険料控除」欄に、計算した控除額を記入すれば完了です。
なお、払いすぎた税金が還付されるのは、確定申告のあと1ヶ月くらいしてからです。
控除を受ける際の注意点
控除の対象とならないケース
ここまで学資保険での生命保険料控除についてみてきました。
学資保険の全てにおいて生命保険料控除が受けられるとは限らず、控除の対象とならないケースもあるため注意が必要です。
生命保険料控除の対象とならないケースには、以下のようなものがあります。
学資保険の保険料を滞納したケース
学資保険の保険料を滞納した場合、生命保険料控除の対象にはなりません。
保険会社から10月から11月頃に郵送されてくる「生命保険料控除証明書」には、その年に支払われる見込みの保険料が記載されています。
事務手続きの関係上「生命保険料控除証明書」は、通常では9月の段階で9ヶ月分の保険料の支払いが確認できた場合や、10月上旬に必要な保険料の支払いが確認できた場合に発行されます。
もし途中で保険料を滞納してしまった場合でも、毎月口座振替で月払いしているケースなら、翌月に2ヶ月分の保険料がまとめて引き落としされます。
そのため、滞納したままになることはあまりありませんが、滞納したのがたった1回分の保険料であったとしても、その年の生命保険料控除の対象外となってしまいます。
年内に滞納した保険料を納めておけば再び控除の対象となるため、できるだけ早めに納付したいものです。
学資保険の保険期間が5年未満のケース
保険期間が5年未満の学資保険は、生命保険料控除の対象とはなりません。
ほとんどの学資保険は、お子さんが小さいうちに加入して15年から20年以上という長期間の契約が続くものです。
しかし、最近ではお子さんが12歳になるまで加入することができるタイプの学資保険も登場しているため、加入時期や契約期間によっては、保険期間が5年に満たないケースもありえます。
このような学資保険に加入している場合には、残念ながら生命保険料控除の対象外となってしまうのです。
保険料控除を受けたいのであれば、保険期間が5年以上になるように加入時期や契約期間を設定する必要があります。
傷害特約などは控除の対象とならないことも
学資保険に、子どもの怪我に備えて「傷害特約」などを付帯している方もいます。
しかし、平成24年1月1日以降に契約または更新・中途付加した学資保険の特約のうち、傷害特約や災害割増特約についての保険料は、生命保険料控除の対象とならないものがあるのです。
詳細は、契約している保険会社に確認すれば確実です。
新旧の学資保険を合算するケース
平成24年1月1日以前と以降に加入した学資保険がある場合、生命保険料控除の計算方法が新制度と旧制度で異なるため、合算するケースでは注意が必要です。
多くの場合、所得税控除の限度額が高くなる新制度の方がお得となりますが、新制度の介護医療保険料控除にあたる区分の控除額が20,000円以下で、旧制度適用の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額がそれぞれ40,000円以上となっているケースでは、旧制度の一般生命保険料控除で計算したほうが控除額は大きくなります。
また、控除申請では新制度と旧制度の両方を合算して申告することができます。
この場合、介護医療保険料以外の区分での新旧合計額の上限は、所得税で40,000円、住民税で28,000円となります。
年末調整で申請を忘れてしまったら
サラリーマンの方が、もし年末調整で生命保険料控除の申請を忘れてしまってもあきらめる必要はなく、自分で確定申告を行えば大丈夫です。
確定申告の方法は「自営業者は確定申告で」の項で詳しく解説しています。
なお、毎年確定申告の期間は税務署や申告会場が大変混み合いますが、サラリーマンの方の生命保険料控除は還付申告なので、確定申告の時期を待たずに1月から受け付けてもらえます。
さらに、還付申告は保険料を支払った翌年の1月1日からの5年間申請できるので、5年以内に申請漏れがあれば早めに還付申告をすませておきましょう。
学資保険も年末調整で申告を忘れない
学資保険は年末調整で所得税から40,000円、住民税から28,000円控除されます。
また、配偶者名義でも申告できるのです。
さらに年末調整で申告し忘れても、あとから還付申請できることも解説しました。
決して安くはない学資保険の保険料ですから、保険料控除申請できっちり税金を取り戻すようにしましょう。

